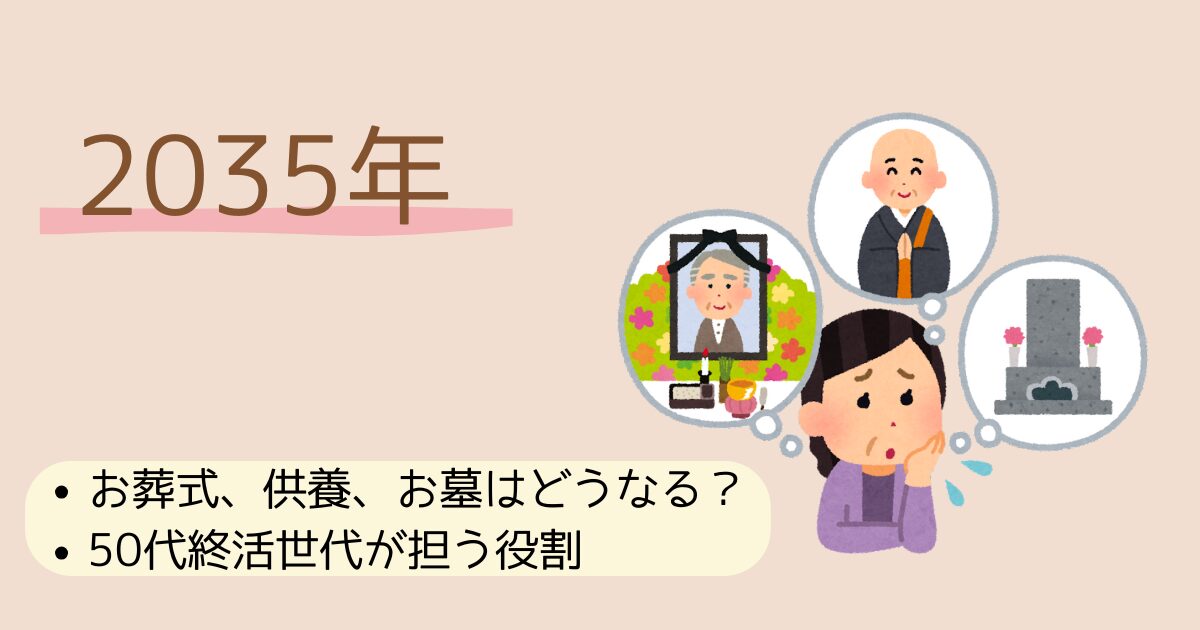少子高齢化が加速し、価値観が多様化する中で、日本のお葬式や供養、お墓の在り方は大きく変わりつつあります。
特に2035年には、今の50代が高齢期に入り、これらの在り方が一層変化することが予想されます。
- 2035年のお葬式・供養・お墓がどのように進化するか予想
- 50代で終活を進める人々が担う重要な役割
- 50代の終活者がもたらす影響
【2035年の葬儀】どうなる?

現状でも家族葬や直葬(火葬のみ)が主流になりつつありますが、2035年には以下のような形が一般的になっているでしょう。
直葬・家族葬のさらなる普及
- 少子高齢化により、葬儀に参加する親族が減少
- 費用を抑えたシンプルな葬儀が主流に・・
- 自宅や小規模なホールでの個別の「お別れ会」が増加
オンライン葬儀・デジタル追悼の普及
- 遠方の親族がオンラインで葬儀に参加することが一般化
- バーチャル空間での「メタバース葬儀」も登場
- 故人の生前の記録をデジタルアーカイブ化し、オンラインで追悼できる仕組みが定着
AIによる葬儀プランニングと進行
- AIが故人の人生や価値観を分析し、最適な葬儀プランを提案
- 葬儀の進行やナレーションもAIが担当し、よりパーソナライズされた式に・・
【2035年の供養】どうなる?

デジタル供養の拡大
- クラウド上に「デジタル墓地」を作り、家族がどこからでもアクセスできる
- AIが故人の言葉や思考を再現し、家族との会話が可能
- スマートフォンやVRを活用した「デジタル追悼空間」の普及
自然葬・エコ供養の主流化
- 環境負荷の少ない「樹木葬」「海洋散骨」がより一般的
- 遺骨を肥料化し、木や花を育てる「循環型供養」が標準化
- 火葬の代替として「水葬」や「バイオ分解葬」が導入される可能性
供養のパーソナライズ化
- 故人の趣味や個性に合わせた供養方法が普及
- 遺骨をペンダントやアート作品として保存する「記念供養」が増加
- 家族それぞれが自由な形で故人を偲ぶ文化が根付く
【2035年のお墓】どうなる?

お墓の「非物理化」が進む
- 土地の制約や管理の負担軽減のため、「クラウド墓地」が普及
- デジタル上で家系図や供養の記録を残す新しいサービスが登場
- 墓石を持たず、家族で共有する「合同供養スペース」が拡大
既存の墓地の統廃合が進む
- 墓じまいの増加により、過疎化する墓地が増加
- 寺院や自治体が「墓じまい支援サービス」を展開
- 共同墓や合葬墓の選択肢が増え、個別の墓地の必要性が低下
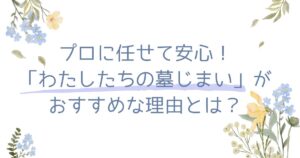
日本は進むのが遅い現実・・

日本は伝統や文化を重視する国であるため、技術や価値観が進化しても、それを取り入れる速度が他国より遅い場合があります。
以下の理由で、日本の葬儀や供養の進化は少しゆっくり進む可能性があります。
伝統文化と宗教観の根強い影響
日本では仏教や神道に基づいた葬儀・供養の形式が根強く残っており、特に高齢層は伝統的な形式を重視する傾向があります。
若い世代が新しい価値観を受け入れても、高齢者の影響力が強い社会では、大きな変化には時間がかかるでしょう。
社会の同調圧力
日本では「世間体」や「周囲との調和」が重要視されるため、家族や親戚、地域の目を気にして新しい形式を選びにくい人も多いでしょう。
たとえば、海洋散骨や樹木葬のような自然葬は増えつつありますが、「普通のお墓を持たないなんて…」という声がまだ残るかもしれません。
法規制や制度の整備が遅い
新しい供養方法やデジタル技術が登場しても、法整備や行政の対応が追いつかない可能性があります。
たとえば、海洋散骨やデジタル墓地などは、法的な扱いや社会的な合意形成が追いつかないため、普及に時間がかかるかもしれません。
技術革新に対する慎重な姿勢
日本は技術大国でありながら、高齢層を中心に新技術に対して慎重な姿勢をとることが多いです。
例えば、メタバース葬儀やAIを使った供養が海外で普及しても、「実際に人が集まる葬儀が一番」という意見が根強い可能性があります。
少子高齢化の影響
少子高齢化がさらに進むことで、葬儀や供養に使えるリソース(費用や人手)が減少し、変化を受け入れる余裕がない場合も考えられます。
また、高齢者層が新しいスタイルを理解・受容するのには時間がかかるかもしれません。
変化は必ず起こる
ただし、日本も少しずつ変化していくのは確実です。
- 若い世代を中心とした変化
- 20〜40代の世代は伝統に縛られにくく、個人主義的で合理的な選択をする傾向がある
- こうした層が主導する形で、新しい供養方法やデジタル化が徐々に広がる
- 都市部から地方へ広がる変化
- 東京や大阪など都市部では、土地不足やライフスタイルの多様化により新しい供養スタイルが早く普及し、それが徐々に地方にも広がっていく可能性がある
- 環境意識の高まり
- 気候変動や環境問題への意識が高まる中で、火葬に代わるエコフレンドリーな方法(樹木葬や水葬など)が自然に受け入れられるように・・
日本の未来像:ゆっくりだが確実に変わる
日本は進むのが遅いかもしれませんが、一度社会的な合意が形成されると、新しいスタイルが急速に広がるという側面もあります(例:キャッシュレス化やリモートワークの普及)。
2040年代には、「伝統を残しながらも多様性を取り入れた日本独自の弔いの文化」が形成されている可能性が高いです。
【2035年】10年後の葬儀・供養・お墓はこうなる!?
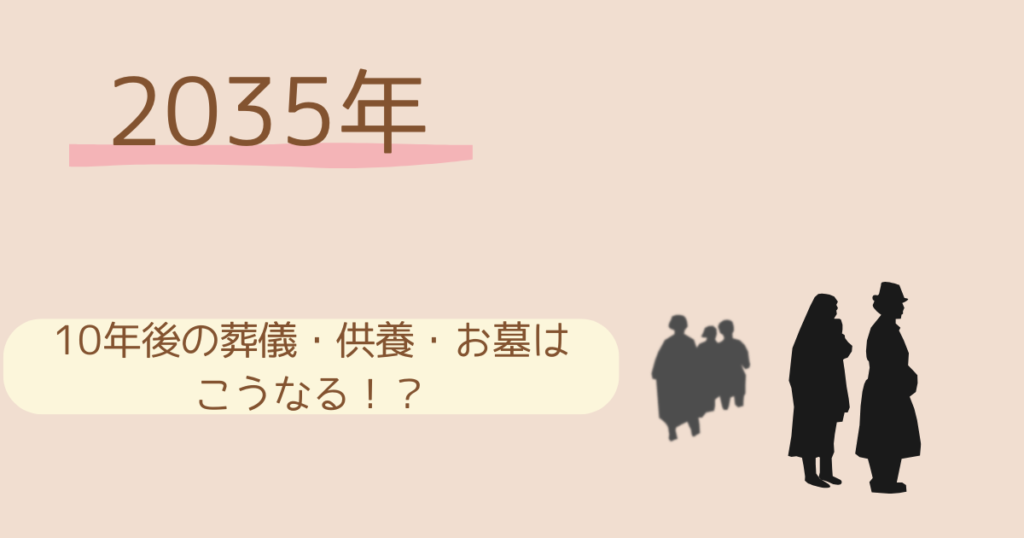
今から10年後の2035年、私たちが知っている葬儀や供養のカタチは大きく変わっているかもしれません。
少子高齢化や価値観の多様化、そして技術の進化によって、従来の形式に縛られないスタイルが主流になる可能性があります。
- 葬儀 より簡素化し、個人の人生を反映したパーソナライズ化が進む
- 家族葬や直葬が当たり前になり、映像や音楽を使ったオーダーメイドの葬儀が一般的になるでしょう
- 供養 デジタル化が進む
- メタバースやクラウド上に「デジタル墓地」が設けられ、どこからでも故人を偲べる環境が整備されるかもしれません
- お墓 概念が変わる
- 自然と共生する形の樹木葬や海洋散骨がさらに広がり、伝統的なお墓に代わる新しい供養方法が選ばれる時代が到来しそうです
 あきな
あきなあと10年でここまで変わるかも・・

20年後くらいかな?
こうした変化が予想される中で、「今」の50代はその未来を準備し、切り拓く重要な世代と言えるでしょう。
50代の終活世代が担う役割とは?
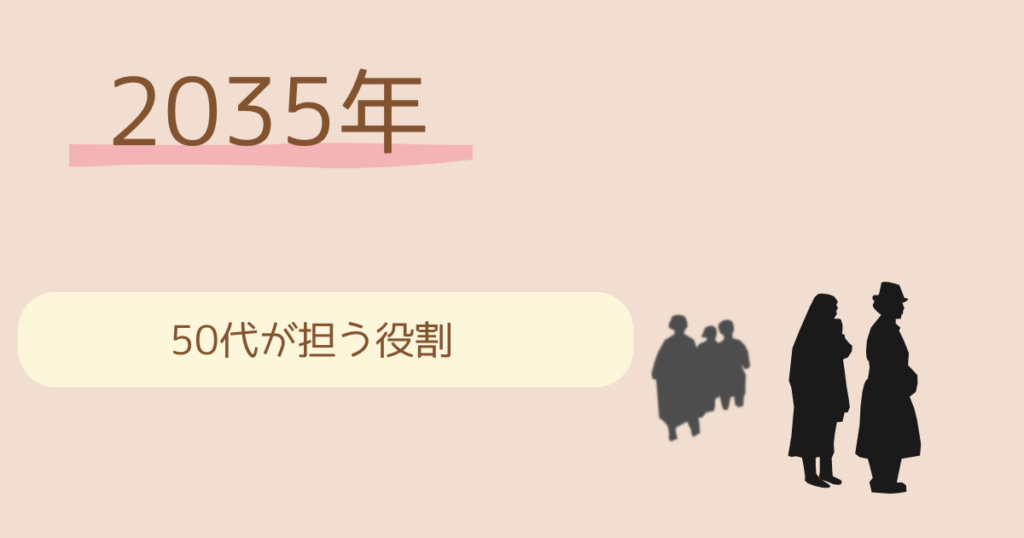
このような変化が予想される中で、現在50代の人々が未来の供養文化を形成する大きな役割を担っています。
 あきな
あきな海洋散骨や墓じまいを、今のうちから選択して取り入れようとしてる50代の終活してる人たちが、未来の葬儀などの形式を開拓してくのかもですね・・
価値観の変化をリードする世代
- 伝統と新しい価値観の橋渡し世代
- 50代は、親世代(70〜80代以上)の伝統的な考え方を尊重しつつ、自分自身の供養では合理性や自由さを求める世代
- 親の供養に伝統的な形式を採用しながら、自分自身の終活では新しい選択肢を積極的に取り入れることで、両者をつなぐ重要な役割を担う
- 情報収集能力の高さ
- デジタル技術にもある程度慣れ、SNSやブログ、専門サイトなどから積極的に情報を収集する世代でもある
- たとえば、海洋散骨や墓じまいといったテーマをブログやSNSで発信することで、他の世代への影響力を持つ可能性がある
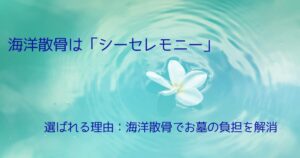
墓じまいや海洋散骨が社会に与える影響
- 供養の形式に対する柔軟性を広める
- 墓じまいや海洋散骨を選択することで、「必ずしもお墓が必要ではない」「供養は形式よりも想いが大切」という新しい価値観を周囲に伝える役割を果たす
- このような選択肢が一般化すれば、親世代や子ども世代にとっても新しい供養方法が受け入れやすくなる
- 供養の経済的・環境的な側面の再考
- 墓じまいの決断や自然葬の普及は、「土地や資源を必要以上に消費しない」という考えを広めるきっかけとなる
- この動きが加速すれば、2035年以降の供養文化のエコフレンドリー化がさらに進む
50代終活世代の影響力
- 「実体験の発信」が変化を促す
- 50代で終活に取り組む人たちが、自身の体験をブログやSNS、YouTubeなどで共有することで、多くの人々に「新しい選択肢」を提示する
- たとえば、海洋散骨や墓じまいの具体的な費用感や手続き、心の変化を発信することで、他の世代が同じ道を選びやすくなる
- 次世代への教育的影響
- 50代の終活世代が自身の子ども(20〜30代)に対して新しい供養形式の選択を伝えることで、次の世代にも「形式に縛られない供養」が広がる土壌を作る
- これが未来の供養文化の基盤になる可能性がある
海洋散骨の実体験はコチラ

海洋散骨や墓じまいが未来を開拓する理由
- 自然葬の先駆者としての役割
- 今の50代が「自然と共生する供養方法」を選ぶことで、海洋散骨や樹木葬の普及に貢献する
- これが標準的な選択肢として定着すれば、2040年には「自然と共存する供養」が一般的な価値観となる可能性がある
- 経済的負担の軽減を示す成功例
- 墓じまいや海洋散骨の経済的な合理性(維持費や負担が少ないこと)を具体的に示すことで、他の人々にも「負担を減らす供養の選択肢」として注目される
- これにより、終活を検討していなかった層にも影響を与える可能性がある

未来予測と、50代のわたしたちが次世代へ繋げる役割ということ分かった!
 あきな
あきなでは、実践例や具体的な方法についてお話しします
未来への終活準備:今できることと次のステップ
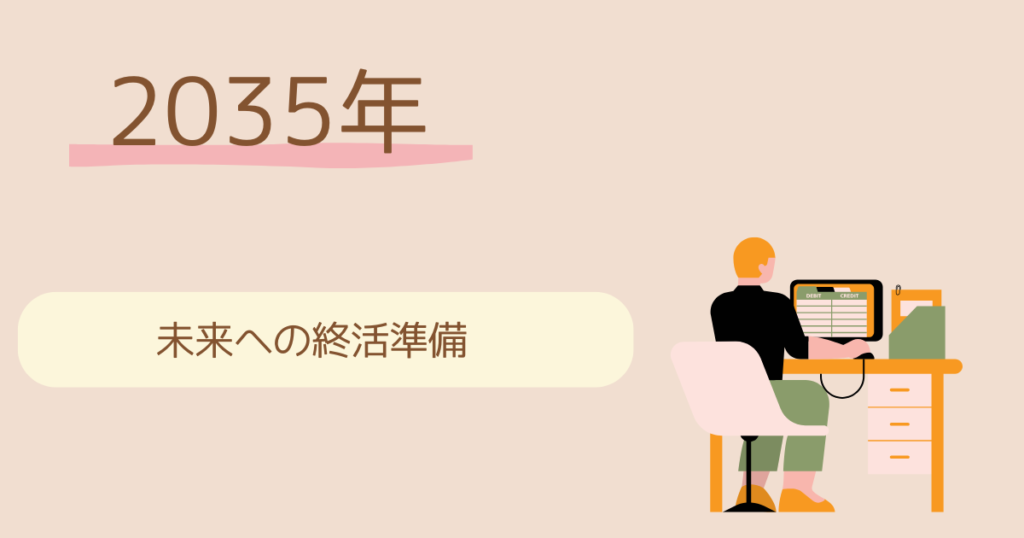
終活を始めたものの、「エンディングノートを書いた」「遺言書を作成した」だけで終わっていませんか?
終活の本当の目的は、自分の意思を整理し、家族が困らないよう準備を整えることです。
終活を進めた後の「次のステップ」とは?
自分に合った葬儀・供養・お墓を決める
- 伝統的なお墓に入るのか、それとも自然葬を選ぶのか?
- 海洋散骨や樹木葬など、現代的な供養方法を検討する
- デジタル供養やオンライン墓地の可能性を考える
家族と話をする
- どんな供養を希望しているのか、家族に共有する
- 家族の考えを尊重しながら、意見をすり合わせる
- 墓じまいや家の管理をどうするか話し合う
準備を実際に進める
- 事前に契約できる「生前予約」を検討する
- 永代供養や合祀墓など、費用面や管理の手間を考慮する
- デジタル資産(SNS、ブログ、メールアカウントなど)の整理も進める
今後の傾向を知っておこう
葬儀(お葬式)・供養・お墓の主流は今後も変化していきます。
これから10年の間にどのような選択肢が広がるのかを知ることで、自分に合った方法を見つけやすくなります。
樹木葬・海洋散骨の普及
- 環境負荷を抑えた供養として、多くの人に受け入れられる
- 維持費や管理の手間が少なく、家族の負担を減らせる
デジタル供養の一般化
- クラウド上で故人を偲ぶ「オンライン墓地」
- AIが故人の言葉を再現し、家族が対話できるサービスの登場
供養の個別化・多様化
- 遺骨をダイヤモンド化する、ペンダントにするなど、オーダーメイドの供養
- 好きな場所に散骨する「思い出供養」
50代で終活をする人が今すぐ取り組むべきこと
50代の今からできることがたくさんあります。
- 費用面を考えて準備する
- 葬儀・供養・お墓の種類ごとの費用を比較し、計画的に準備する
- 生前に契約できる「事前申し込み」などを活用する
- 自分の希望を明確にし、家族と共有する
- エンディングノートに供養の希望を書き記す
- 家族と定期的に終活について話し合う
- デジタル終活を進める
- SNSやメールアカウントの管理方法を決める
- デジタル遺品を整理し、家族がアクセスできるようにする
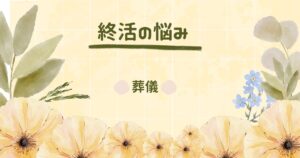
資料請求や見積依頼はコチラ
| サイト名 |  【安心葬儀】 | 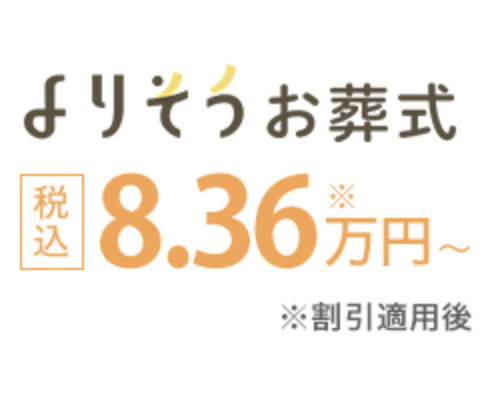 よりそうのお葬式 | 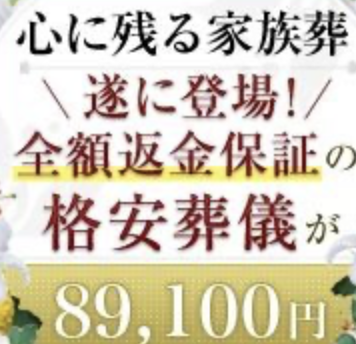 心に残る家族葬 |
|---|---|---|---|
| 全国対応 | 全国7,000以上の 葬儀社 | 全国5,000以上の 提携葬儀場 | 全国の提携式場数 3,000以上 |
| 葬儀プラン名と金額(税込) 家族葬1日タイプ | 一日葬 200,000円 | よりそう家族葬1日プラン 330,000円 | 心に残る一日葬 335,000円 |
| 〃 家族葬2日タイプ | 家族葬 300,000円 | よりそう家族葬2日プラン 438,900円 | 心に残る家族葬 495,000円 |
| 〃 火葬のみタイプ | 火葬・直葬 100,000円 | よりそう火葬式シンプルプラン 100,100円 | 心に残るシンプル葬 89,100円 |
| 資料請求や事前相談で割引 | あり | あり | あり |
| 24時間365日通話相談 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 資料請求やご相談はコチラ→ | 【安心葬儀】 | よりそうのお葬式 | 心に残る家族葬 |
まとめ:10年後(2035年以降)のお葬式・供養・お墓に関する予想と50代の終活者の影響
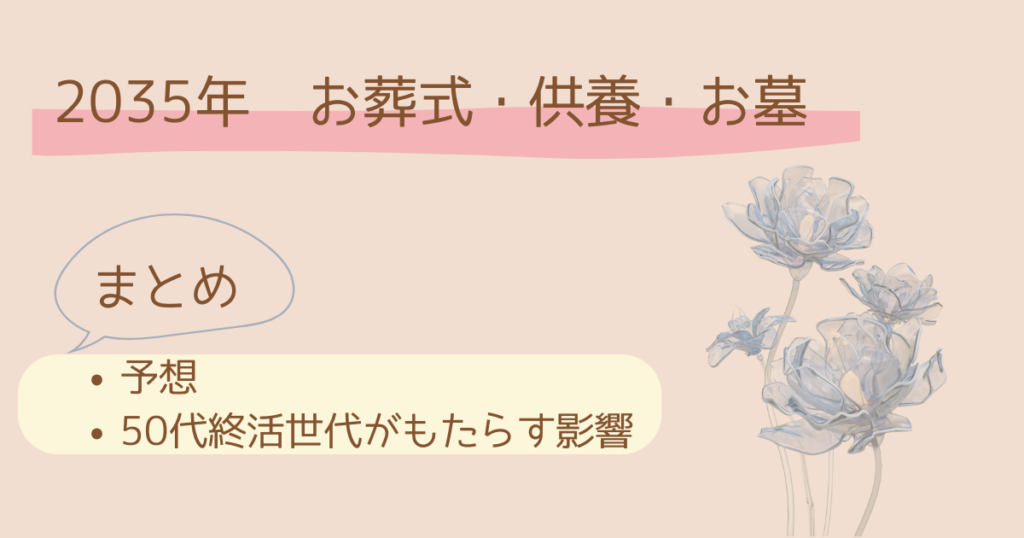
2035年には、葬儀や供養、お墓の形が大きく変わることが予想されます。
その変化を受け入れ、自分にとって最適な供養の形を選ぶために、今のうちから終活を進めることが重要です。
| 項目 | 未来の予想(2035年以降) | 50代の終活者がもたらす影響 |
|---|---|---|
| お葬式 | 家族葬・直葬が主流に オンライン葬儀やメタバース供養が普及 AIを活用した追悼サービスが登場 | シンプルな葬儀を選ぶ傾向が加速し、オンライン葬儀の普及を後押し AI遺言やデジタル追悼サービスを導入する人が増える |
| 供養方法 | 海洋散骨や樹木葬が一般化 デジタル供養(VR・AI追悼)が普及 遺灰を加工したジュエリーや宇宙葬も一般的に | 「お墓を持たない」供養を選ぶ人が増え、海洋散骨や樹木葬の需要が拡大 デジタル供養の認知が進み、利用者増加 |
| お墓の形 | 永代供養墓や合葬墓が標準化 都市部では「デジタル墓」や「バーチャル霊園」が登場 | 墓じまいが加速し、合同墓・樹木葬を選ぶ人が増える 従来の墓地需要が減り、デジタル墓や共同墓の整備が進む |
| 遺影・遺言 | AIによる生成遺影・デジタル遺言が普及 生前に録音・録画したメッセージを残すのが一般的に | デジタル終活の意識が高まり、AI遺影やビデオメッセージを準備する人が増える |
| 家族との関係 | 「家族に負担をかけない終活」が主流に 終活の情報共有がスムーズになり、意思決定がデジタル化 | 50代のうちにエンディングノートやデジタル終活を実施することで、家族の負担軽減につながる |
このように、現在50代の人々が終活を進めることで、2035年以降の供養やお墓のスタイルが大きく変わると考えられます。
 あきな
あきな特に「負担をかけない」「持たない供養」「デジタル活用」の流れが加速しそうです
50代の終活者がすべきこと(2035年以降を見据えて)
デジタル終活を進める
- デジタル遺言を準備する
- エンディングノート・デジタル遺言書サービスの活用
- SNS・メール・サブスクの整理
- アカウントの削除・管理方法を家族と共有
- AIや動画でメッセージを残す
- 未来の家族や友人に向けたビデオレター
お墓・供養の準備をする
- 墓じまいを検討する
- 自分の代でお墓を閉じるか、継承しない供養方法を考える
- 海洋散骨・樹木葬を調査する
- 費用や手続き、信頼できる業者のリサーチ
- 合同墓・永代供養墓の選択肢を確認
- 個人で維持不要な供養方法を選ぶ
葬儀の簡素化を検討する
- 家族葬・直葬を希望するか決める
- 規模や方法を具体的に検討
- オンライン葬儀の可能性を考える
- 遠方の家族・友人が参列しやすい形式を検討
- 事前に葬儀社をリサーチする
- 無駄な費用を抑えるためにプランを比較
財産・相続の準備をする
- 遺言書を作成する
- 法的効力のある公正証書遺言を準備
- 家族に財産状況を共有する
- 突然の相続トラブルを防ぐ
- 終活信託や家族信託を活用する
- 認知症になる前に資産管理の仕組みを作る
未来のライフスタイルを考える
- 介護される側の準備をする
- どこで・誰に・どのようなケアを受けるか考える
- 老後の住まいを検討する
- 持ち家・賃貸・高齢者向け施設の選択
- 健康維持に努める
- 認知症予防・フレイル対策・健康管理
家族や周囲と終活について話す
- エンディングノートを作成・共有する
- 家族に希望を伝え、負担を減らす
- 家族と供養や葬儀の意向を話し合う
- 意思を伝えることで後の混乱を防ぐ
- 終活の進捗を定期的に見直す
- 状況の変化に応じてアップデート
これを読めばバッチリです!
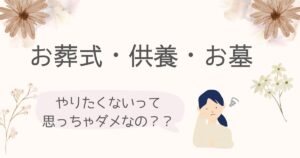
自分らしい終活を考え、未来に向けた準備を始めましょう。